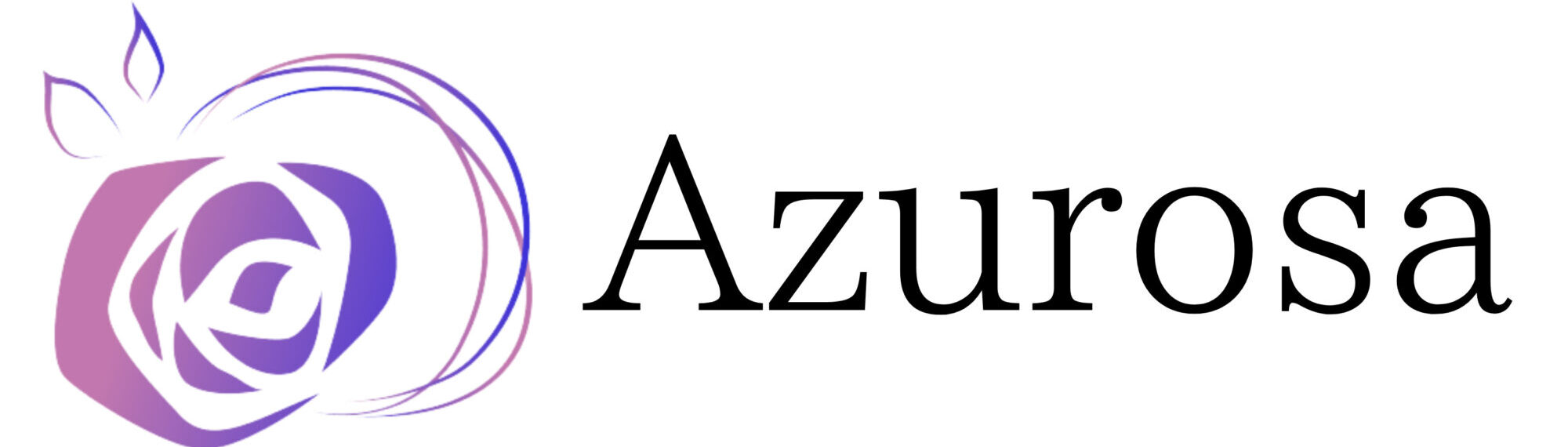プリザーブドフラワーを作ってみたいけど、「材料って何が必要?」「全部揃えるのって大変そう…」と悩んでいませんか?
実際、多くの初心者が、道具や液体の名前すら分からずに困ってしまうのが現実です。
でも安心してください。この記事では、プリザーブドフラワーの材料に関する基本から、揃え方、選び方、よくある失敗例まで、誰でも分かるように解説します。
しかも、すでに材料を揃えて何度も成功させている筆者の実体験をもとに、現場で本当に使えるテクニックだけを厳選してお届け。
高価な道具を揃えなくても、100均やネット通販で手軽に始める方法も紹介しています。
プリザーブドフラワー作りを始めるなら、「材料の選び方」が成否を分けます。
この記事を読めば、迷うことなくあなたにぴったりの材料を揃えられるはずです。
ぜひ最後まで読んで、あなたの理想のアレンジをスタートさせましょう!
目次
プリザーブドフラワーとは何?材料を語る前に理解したい基礎
まず最初に「プリザーブドフラワー(preserved flower)」って何かをきちんと押さえておきましょう。材料や加工の話に入る前に、この基礎を理解しておくことで、後の選び方や注意点も腑に落ちやすくなります。
プリザーブドフラワーとは
定義・特徴
プリザーブドフラワーとは、生花を特殊な加工で保存可能な状態にしたお花のことです。具体的には、生花の水分や樹液を一度抜き取り、それをグリセリンや保存液、染料などを含む溶液で置き換える処理を施すことで、「枯れない」「見た目を長く保つ」状態にします。
この加工により、柔らかな手触りや自然な質感を残しつつ、水やり不要で色あせもしにくくなります。
プリザーブド加工された花は、ドライフラワーとも造花とも異なる立ち位置にあり、「生花のような美しさ + 長期保存性」を兼ね備えた存在として人気があります。
なぜこの知識が材料選びに必要か(論点)
材料を選ぶ際には、使われる液体(保存液・染料など)や花材(どの花を使うか)だけでなく、「なぜその材料を使うか」が理解できていると、失敗を避けることができます。たとえば、花材の持ちやすさ、染めムラ、薬液の安全性などは、プリザーブド加工の原理を知らないと見落としやすい部分です。
補助的な情報:保存期間・メリット・デメリット
保存期間の目安
適切な環境下で保管すれば、数年~長期にわたって美しさを保てるとされます。ヨーロッパでは「5〜10年持つ」との見方もありますが、日本では湿気などの影響を受けやすく、一般的には 1~3年程度 が実用的な目安とされています。
メリット
- 水やり不要で手入れが簡単
- 花粉や香りがほとんどないためアレルギーの心配が少ない
- 色あせしにくく、カラーバリエーションが豊富
- 見た目が自然で、本物らしさが残る
デメリット・注意点
- 高温多湿・直射日光に弱い
- 薬液や着色のムラリスク
- 花びらがもろくなったり、割れたりすることもある
- 長期保存には環境管理が重要
まとめ
プリザーブドフラワーとは、生花を特殊処理して「枯れないように保存された花」のことです。ドライフラワーや造花とは異なり、生花のような質感を残しつつ、比較的長持ちするという利点があります。ただし、保存条件や素材・薬液の選び方次第でその寿命や仕上がりが大きく変わるため、これを理解したうえで材料選びや加工に進むことが非常に重要です
必須の基本材料一覧:これだけは揃えよう
プリザーブドフラワーを自宅で作るには、特別な機械や高価な設備は必要ありません。しかし、最低限揃えておくべき基本材料はいくつかあります。この章では、初心者でもすぐに始められるよう、必要な材料をわかりやすく紹介していきます。
加工液(脱色液・着色液・保存液)
プリザーブドフラワーを作るうえで欠かせないのが「加工液」です。生花の色を抜く「脱色液」、好みの色に染める「着色液」、そして花を柔らかく保ちながら長持ちさせる「保存液」の3種類が基本です。
最近では、初心者向けに3種類の液がセットになった加工液キットも販売されています。調合の手間が省けるため、最初のうちはキットを利用するのが安心です。
エタノールやグリセリン、水などをベースにした液体が主流ですが、メーカーごとに配合が異なるため、説明書をしっかり読みながら使いましょう。
花材(使用する生花)
使用する花材は、プリザーブド加工に向いた種類を選ぶことが大切です。特に人気なのはバラ、あじさい、かすみ草など。これらは花びらがしっかりしていて、加工後の仕上がりが美しいことで知られています。
購入する際は、新鮮で傷のない花を選びましょう。花の厚みや形が均一であるかどうかも、完成度に影響します。特に色の濃い花は脱色が難しいため、初心者には淡い色の花をおすすめします。
また、グリーン(葉物)や実ものなども、アレンジに使うと作品に深みが出るため、少量用意しておくと便利です。
器具・道具
作業をスムーズに進めるためには、適切な道具も必要です。代表的なものは以下の通りです。
- ハサミ:茎や花びらを切る際に使用。刃が鋭く、サビにくいものが最適。
- ピンセット:細かい花びらを扱うのに便利。先端が細く、滑りにくいタイプがおすすめ。
- 容器:加工液を入れて花を浸けるための容器。ガラスや耐薬品性プラスチックが向いています。
- 使い捨て手袋・マスク:薬液に触れないようにするための必需品。安全のために必ず用意しましょう。
補助材料(あると便利なもの)
必須ではありませんが、あると便利な補助材料もいくつかあります。
- シリカゲル・乾燥剤:花を乾燥させる際に使います。乾燥ムラを防ぎ、花の形を保ちやすくなります。
- UVカットスプレー:完成した作品を日光から守り、色あせを防ぎます。
- フローラルフォーム・ワイヤー・テープ:アレンジ時に使用する道具。花を固定したり、形を整えたりするのに役立ちます。
- ガラスドームやケース:作品を飾るための容器。ほこりや湿気から守る役割もあります。
材料を揃えるときのポイント
初めからすべてを完璧に揃えようとせず、まずは「基本セット+使いたい花材」で十分です。慣れてきたら、必要に応じて道具や補助材料を買い足すのがおすすめです。
また、近年ではスターターセットが多数販売されており、加工液・道具・花材がセットになっているものもあります。こういったセットを利用すれば、最小限のコストで始められるのも魅力です。
まとめ
プリザーブドフラワー作りに必要な材料は、「加工液」「花材」「器具」「補助材料」の4種類です。それぞれに役割があり、揃えることで自宅でも本格的な制作ができます。
最初は無理なく、必要最低限の道具から始めて、徐々に自分のスタイルや目的に合わせてカスタマイズしていくとよいでしょう。
材料の選び方と品質の見極めポイント
まず結論から言うと、良い材料を選ぶには「素材の性質・扱いやすさ・安全性・コストバランス」の4つを重視すれば、失敗を減らせます。
以下でその理由を示し、具体的な選び方と注意点を交えて解説します。
なぜこの4つを重視するのか(理由)
- 素材の性質:花材や液体が変質・劣化しやすいものだと、色むら・花びらの劣化が起きやすい。
- 扱いやすさ(操作性):初心者でも使いやすい液体や道具を選ばないと、作業中に材料を痛めたりミスを誘発しやすい。
- 安全性:薬液を使うため、有害性・揮発性・皮膚刺激性などを見極めないと、健康・作業環境にリスクがある。
- コストバランス:高品質でも価格が高すぎると続けづらい。最初はコスパの良いものから入り、その後グレードを上げるのが賢明。
これらをバランスよく見て選ぶことで、「見た目はいいがすぐ劣化した」「液が強すぎて花が壊れた」といったよくあるトラブルを避けることができます。
具体的な選び方・チェックポイント(例)
以下、それぞれの観点から具体例をあげながら、どこをチェックすればいいかを説明します。
1. 素材の性質を見極めるポイント
花材(花・葉・実もの)
- 花弁の厚さ・コシ:薄すぎると液でふやけて裂けやすい。厚みがありしっかりしたものを選ぶ。
- 元の色調・模様:濃すぎる原色は脱色・着色でムラが出やすい。淡色寄りだとコントロールしやすい。
- 傷・斑点・痛みの有無:元から傷があると加工後に目立つ。傷のない新鮮な素材を選ぶ。
(例:バラ、あじさい、かすみ草などが初心者向きとされており、これらは比較的加工耐性が高い花材として紹介されている) アモローサ モデルノ+1
2. 扱いやすさ・操作性での選び方
液体(脱色液・着色液・保存液)
- 濃度・希釈のしやすさ:濃縮タイプだと失敗しやすい。最初は希釈済み・取扱説明書が明瞭なものを選ぶ。
- 調合の自由度:染料を混ぜやすいタイプ、色の調整しやすい処方だとアレンジ幅が広がる。
- 安定性:変質しにくい保存性のある処方のもの。保存期間が短い液だと使い切る必要がある。
道具・器具
- 耐薬性素材:薬液に強い素材(ステンレス、耐薬性プラスチックなど)でできている。
- 操作性:ハサミの切れ味、ピンセットの先端形状、グリップ感などが扱いやすいもの。
- 清掃・メンテナンス性:洗いやすい構造なら、残液・汚れが残りにくく長期使用に向く。
3. 安全性を重視した選び方
- 安全データシート (SDS):化学薬品であれば、成分・安全性・注意点が記載された資料があるものを。
- 低刺激・無毒性成分の使用:手肌にやさしい処方、揮発性の低い液体など。
- 包装・保管形態:密閉性があり蒸発を防げる容器、安全キャップ付き、遮光性のあるボトルなど。
- 取扱説明の明瞭さ:使用方法・廃棄方法をきちんと記載しているもの。
4. コストバランスを考慮した選び方
- 初期費用を抑えたスターターセット:必要最小限をセットにした商品で、無駄買いを防ぐ手段
- 使い切り小容量タイプ:最初は少量サイズで買い、品質を見て後で大容量を検討
- 代替素材の活用:100均品・手芸店素材を賢く併用してコストを下げる(ただし品質チェックは必須)
- 継続コストも視野に入れる:材料を揃えて終わりではなく、消耗品・補助剤のコストも見込む
まとめ
材料の選び方で最も大事なのは、素材の性質・扱いやすさ・安全性・コストバランス をバランス良く見ることです。
これらを意識して選べば、見た目も品質も長持ちするプリザーブドフラワー作りに近づけます。
購入先・仕入れ先ガイド(国内・オンライン)
プリザーブドフラワーの材料を揃えるとき、どこで買うか は非常に重要なポイントです。品質・送料・在庫などが場所によって変わるため、実店舗・通信販売それぞれの特徴を理解しておきましょう。
実店舗で買うメリットと注意点
実際に手にとって選べるのが実店舗の最大の強みです。色・質感・状態を目で見て確認できるので、特に初めて材料を選ぶ人には安心感があります。
- 花屋・プリザーブド専門店
銀座などには、日本初のプリザーブドフラワー専門店「ベル・フルール」もあります。
こうした専門店では、材料単体だけでなくセット品やアレンジ例の展示もされており、相談しながら購入できます。 - 資材店・卸売店
東京堂など、造花やプリザーブドの卸売りをしている資材店があります。e-
業務向けの品揃えが多いため、まとめ買い・特殊サイズの材料を探したい人に向いています。 - 手芸店・クラフト店・100均
ハサミ・道具類や補助材料(ワイヤー、スポンジなど)は、手芸店やクラフトショップで揃いやすいです。
また、100円ショップでも花材の一部や装飾パーツが手に入ることがあります。 - 注意点
実店舗では在庫が限られていたり、取扱品目が偏っていたりすることが多いです。店舗によっては特定の商品しか扱わないため、目当ての材料があるなら事前に問い合わせておくと安心です。
通信販売・通販サイトを利用するメリット
オンラインで購入するメリットは、選択肢の幅と利便性の高さです。以下のような通販サイトが素材入手に適しています。
- はなどんやアソシエ
プリザーブドフラワーの花材や資材を豊富に揃えた通販サイト。即日発送品も多いのでスピード面でも頼りになります。 - ケーネクスト
プリザーブド花材専門の通販店。ローズ、あじさい、グリーン類など幅広く扱っています。 - 大地農園
プリザーブド・ドライフラワー素材の老舗メーカー。製品ラインナップが広く、信頼性も高いです。 - AUBE(オーブ)
プリザーブドフラワー専門店で、花材販売ページも用意されています。 - 楽天市場・その他モール
「プリザーブドフラワー 花材」で検索すると、多数の卸売・小分け素材が出てきます。
通販の強みは、実店舗では手に入らない珍しい色・素材・サイズを選べること。また、レビューや評価を参考にしながら選べる点も安心材料になります。
ただし注意すべき点もあります。送料や梱包状態、商品の扱われ方(実物と写真の違い)などをよく確認しましょう。
国内 vs 海外輸入、どちらを使うか
素材をより安く、より多様に手に入れたい場合、海外からの輸入という選択肢もあります。ただし、次の点に注意が必要です。
- 輸送コストと関税:輸入時の送料や関税が思った以上にかかることがあります。特に重量・ボリュームがある花材はコストが跳ね上がります。
- 品質と検品:輸送中の破損や劣化リスクが高く、品質管理をしっかりしている業者を選ぶべきです。
- 納期の不確実性:到着まで時間がかかったり、通関手続きで遅れたりすることがあります。
- 安全性・輸入規制:植物素材には検疫などの規制がかかることもあるので、輸入可否を確認すること。
初心者のうちは国内の通販や卸店を利用し、慣れてきたら海外素材を試すという流れがおすすめです。
購入時にチェックすべきポイント
通販・店舗問わず、材料を選ぶときは以下のポイントを確認すると失敗しにくいです。
- 品番・ロット表示:同じ素材でもロットが異なると色合いや質感が変わることがあります。
- 写真と実物の差:拡大写真で花びらの状態をよく見る、レビューに実物写真があるかチェック。
- 送料・梱包方法:花材は折れ・潰れに弱いため、十分な緩衝材や固定方法がされているかを確認。
- 返品・交換ポリシー:品質不良時の対応が明記されている販売先を選ぶと安心。
- 最小購入単位・切売りの可否:初心者は小ロットで買えるところを選ぶと無駄がありません。
加工液・薬液の種類と使い方をマスターする
プリザーブドフラワーを作るうえで、加工液・薬液の選び方と使い方が仕上がりを大きく左右します。この章では、主要な液体の種類、それぞれの使い方、注意点を丁寧に説明します。
加工液の基本構成と分類
加工液は大きく次のようなタイプに分けられます。
- プリザ液A(脱水・脱色液)
生花の水分や色素を置換・除去する液体。エタノールや他の溶媒が主成分となることが多いです。 - プリザ液B(着色液・保存液)
脱水後の花材に好きな色をつけ、さらに花びらを柔らかく保つ機能を持たせた液体。
また、市販品には以下のような方式もあります:
- 1液タイプ(オールインワン型)
脱水・着色・保存の機能を兼ね備えた液体。工程を簡略化できるため初心者向け。 - 2液タイプ(A液 + B液方式)
脱水・脱色を行うA液と、着色・保存を行うB液を分けて使う方式。コントロールしやすく、仕上がりの調整が可能。
素材や用途に応じて、これらの方式を選ぶことが肝心です。例えば葉物(リーフ)や枝物向けの専用液(リーフ液)という製品も存在します。
液体の使い方・工程の流れ
一般的な2液方式を例に、加工手順と使い方のポイントを説明します。
- 脱水・脱色工程(A液)
生花をA液に浸け、水分と色素を徐々に置換します。時間は素材・厚みによって変わります。濃い色の花は複数回脱色を行うこともあります。
使用中、液が不透明になったら交換タイミングの目安です。 - 洗浄工程
脱色後の残留物を落とすため、淡いA液または中性水洗いを行うことがあります。着色液に影響を与えないためです。 - 着色・保存工程(B液)
洗浄後、B液に浸して色を染み込ませ、同時に保存効果を与えます。B液には「溶剤タイプ」「水性タイプ」があり、混ぜて使うと化学反応を起こす恐れがあるため注意が必要です。
着色ムラを避けるため、液の温度・濃度・浸透時間を調整することが大切です。 - 乾燥工程
着色後、花材を乾燥させて仕上げます。乾燥ムラを防ぐため、風通しのよい場所で陰干しが基本です。
1液タイプを使う場合は、上記の工程が一体化されていて「浸けたまま仕上げ」という方式もあります。手順が簡単な反面、使える素材が限定されることが多いです。
液体を使うときの注意点
- 溶剤・化学反応に注意:着色液にある種の溶剤が使われることが多く、換気や火気管理が不可欠です。
- 混合禁止:溶剤タイプと水性タイプのB液を混ぜると不安定になり、色ムラや薬液の変質を招くことがあります。
- 温度管理:液が冷えすぎたり、強く加熱したりすると性質が変わることがあります。
- 保存方法:直射日光を避け、冷暗所で保管。液が固まった場合、中温のお湯で湯せんすることがあります。
- 液の使い回し回数:花から出た水分や不純物で効果が弱くなります。目安として使い回しは2~3回程度とする業者もあります。
加工液を選ぶときのポイント
- 素材適合性:どの花や葉に使えるか対応表をチェックして選ぶ
- 色展開・染料の品質:色数や発色の幅
- 濃度と希釈の自由度:調整しやすい仕様だと応用が効く
- 安全性・説明の明瞭性:使い方・注意事項が明記されている製品
- 価格とコストパフォーマンス:大容量・小容量の選択肢があるか
安全対策と注意点:失敗を防ぐために
プリザーブドフラワー作りは化学液を使う工程が多いため、安全対策を怠ると事故やトラブルにつながります。また、完成後の管理方法を誤ると見栄えが傷んでしまうので、この章では「作業中の安全対策」と「飾る・保管する際の注意点」の両方を解説します。
作業中の安全対策
換気を徹底する
加工液(特に脱色液や着色液)にはアルコールや有機溶剤が含まれることが多く、揮発性があるものも使われます。作業場所は窓を開ける、換気扇を回すなどして、空気を流すようにしましょう。
火気厳禁
アルコール系溶液を使う場合、火や火花が近くにあると引火する恐れがあります。作業場にはライター、タバコ、ストーブなどを持ち込まないようにしましょう。
手袋・保護具の着用
薬液が肌に触れるのを防ぐため、使い捨て手袋(ニトリル、ラテックスなど)を着けましょう。液が目や衣服に付着しないよう、作業時は保護メガネやエプロンなども使うと安全性が高まります。
液の保管と取扱い
加工液は直射日光を避け、冷暗所に保管するのが基本です。特に低温で固まる可能性がある液体は注意が必要で、温度管理がポイントになります。また、使用後の残液は、メーカーの指示や安全基準に従って適切に処理・廃棄しなければなりません。
混合の危険性に注意
異なるタイプの液(たとえば溶剤タイプと水性タイプ)を混ぜると化学反応を起こし、予期せぬ変化や危険が生じることがあります。特に着色液で混色を試みるときには、相性を確認してから使いましょう。
完成後および展示中・保管時の注意点
湿度と温度管理
プリザーブドフラワーは湿度の影響を強く受けます。湿気が多すぎると色がにじんだり、染料が移ったり、花びらが透明になることがあります。逆に乾燥しすぎても花びらが割れやすくなるため、エアコンや除湿機の風が直接当たらない場所に置くのが望ましいです。
直射日光・強い光の回避
紫外線や強い光は色あせ・変色の原因になります。窓際など日差しが当たる場所は避け、間接光ややわらかな光の下に飾るのが理想です。
色移り・染料のにじみへの注意
濃い色の花材が隣り合わせにあると、湿気や圧力によって色移りが起きることがあります。異なる色同士は一定の距離を取る、または透明ケースに入れて隔離するのが有効です。
飾る場所の選び方
完成品を飾る場所は、風通しが良く、温度変化が小さいところが適しています。湿度が高くなりやすいトイレやバスルーム、キッチンの近くは避けたほうが安全です。ガラスドームや密閉ケースを使えば、ほこりや湿気からも守れ、長持ちさせやすくなります。
ホコリ取り・掃除
ホコリが付くと見た目が損なわれるだけでなく、湿気を呼び込んで劣化を早めることがあります。柔らかい刷毛や絵筆で優しく払う、またはエアスプレーの冷風を使う方法もあります。ただし、水拭きや化学洗剤の使用は避けましょう(色落ち・変質のリスクあり)。
衝撃・揺れ対策
プリザーブドフラワーは繊細で、強い衝撃や振動が加わると花びらが欠けたり、形が崩れたりします。設置場所は安定した台や棚を選び、触れられにくい位置に置きましょう。
よくある失敗パターンとその対処法
プリザーブドフラワー作りで多くの人がぶつかる失敗には共通点があります。それを知っておくと「これはよくあることだな」と冷静に対応でき、次回への改善にもなります。以下に代表的な失敗例と、それぞれの対策を紹介します。
花びらがもろくなる・割れる
原因
液が強すぎる、浸漬時間が長すぎる、または急激に乾燥させた場合に起こりやすい現象です。特に薄い花びらや繊細な素材は、薬液への耐性が弱いことがあります。
対処法・予防策
- 最初は薄めの液から始め、徐々に濃度を上げていく
- 花材の厚みを吟味し、繊細な花は避けるか短時間処理
- 乾燥時は風通しをよくし、直接風を当てず徐々に乾かす
- 液によっては添加剤で柔らかさを補うタイプを選ぶ
色むら・色落ちが起きる
原因
液の濃度ムラ、着色液の混合ミス、浸漬時間の差異、洗浄が不十分なことなどが要因になります。また、温度変化や乾燥ムラも影響を与えます。
対処法・予防策
- 着色液はよく攪拌(かくはん)し、均一に混ぜる
- 花材全体が液にしっかり浸かるよう落とし蓋などを使う
- 複数回に分けて着色したり、薄色から重ね塗りする方法を検討
- 着色後すぐに洗浄を行い、余分な染料を落とす
カビ・湿気・変色が発生する
原因
保管環境が湿気が多い・空気の流れが悪い・密閉が不十分な状態にある場合。液残留や未乾燥も原因のひとつです。
対処法・予防策
- 乾燥後はしっかり乾かし、湿気を残さない
- 保管は湿度管理された場所(例えば湿度計を使う)で
- 密閉ケースやガラスドームを利用し、ほこり・湿気を防ぐ
- 完成品を飾る際は時々空気を通すようにふたを開ける
花の形が崩れる・縮む
原因
液への浸け方にムラがある、花を無理に配置したときに圧力がかかる、乾燥時に変形を起こすなどの場合に発生します。
対処法・予防策
- 花材を扱うときはピンセットで優しく扱い、無理な力をかけない
- 液に浸す前に茎を適度に切り揃え、バランスよく配置
- 乾燥時は平らな場所で、重ならないように広げて干す
- 支えや仮固定具(ワイヤー・フォーム)を使って形を保持する
これらの失敗例と対策を知っておくことで、プリザーブドフラワー作りでつまずく確率をぐっと下げられます。
長持ちさせるための補助材料とケア
プリザーブドフラワーは加工後のケア次第で寿命が大きく変わります。この章では、長持ちさせるために役立つ補助材料と、日常的なケアのコツを段落ごとにわかりやすく解説します。
シリカゲル・乾燥剤を使って湿気を制御
完成後の作品を保存する際、湿度が高いと変色・カビ発生・染料のにじみなどのトラブルが起こりやすくなります。シリカゲルや乾燥剤を作品の周囲に置くことで、湿度を抑えて安全な環境を作ることができます。特に密閉ケースの中では、湿気がこもりやすいため、このような乾燥剤の併用が有効です。
また、乾燥剤は定期的に交換するか、再生(乾燥)して再利用できるタイプを選ぶとコストも抑えられます。
UVカットコーティング・スプレーで変色を防ぐ
紫外線はプリザーブドフラワーの色あせ・劣化を進める大きな要因です。完成後、UVカット効果のある透明コーティング剤やスプレーを薄く吹きかけておくと、日光・照明からのダメージを軽減できます。
使用の際は、数回に分けて薄く吹きかけ、完全に乾かしてから重ね塗りするようにしましょう。厚く一度に吹きつけると、ムラや滴の跡が残ることがあります。
ケース・ドーム・密閉容器で物理的保護を
完成品をそのまま空気中にさらしておくと、ほこり・湿気・衝撃によるダメージを受けやすくなります。ガラスドームやアクリルケース、密閉容器などに入れることで、これらのリスクを大幅に減らすことができます。
また、作品とケースの間にクッション材やウレタンフォームを敷くと、振動や揺れによる破損も防げます。
定期的なホコリ除去と環境チェック
作品に付着したホコリは見た目を損なうだけでなく、湿気と結びついて劣化を促すことがあります。柔らかいブラシやエアダスター(冷風)を用いて、やさしくホコリを取り除きましょう。水拭きや湿った布は使わないようにしてください。
また、定期的に作品を目視チェックし、湿度・温度・色あせの進行具合を確認することも大切です。特に春〜夏の高温多湿期には注意が必要です。
展示場所と配置に気をつける
作品を置く場所も耐久性を左右します。直射日光が当たる窓辺や照明の近く、エアコンの直風が当たる場所は避けたほうが無難です。温湿度が安定している部屋を選び、風通しのよい場所に設置するのが理想です。
また、濃い色・淡い色が混ざった作品は、色移りリスクを避けるためにできるだけ別々に配置するか、間隔を空けるように工夫してください。
実例:材料を揃えて作ってみたステップ・工程(素材別)
ここでは、具体的にバラやあじさいなどの素材を使って、材料を揃えてから作品を仕上げるまでの流れを一例として紹介します。ステップごとに注意点も交えつつ説明するので、実際に手を動かすときの参考にしてください。
ステップ0:準備と素材選び
まずは、使いたい花材を選びます。バラやあじさい、かすみ草などはプリザーブドに向く定番素材です。花びらが厚く、傷や茶色い斑点がない、かつ花の形が整っているものを選ぶと仕上がりが良くなります。
次に、材料を揃えます。前の章で説明した「加工液(脱色液・着色液・保存液)」「器具・道具」「補助資材」などを準備しておきます。液体は少量ずつ試せるセット品でも構いません。道具はハサミ・ピンセット・耐薬容器などを用意しておきましょう。
また、作業台周りに古新聞やビニールシートを敷いておくと、液がこぼれても安心です。
ステップ1:水揚げ・下処理
生花を購入してから時間が経っているものは、水分が抜けていることがあります。まずは「水揚げ」を行って、水をしっかり吸わせます。茎を斜めに切る、水中で切るなどの方法があります。これにより、後で加工液の浸透がよくなります。
また、葉やガクを落とすなど余分な部分を取り除くことで、液体の浸透ムラを防ぎ、仕上がりをきれいにできます。
ステップ2:脱色・脱水工程
用意した脱色液に、花材を浸します。液が花全体を覆うようにして、アルミホイルなどで浮き上がりを抑える「落し蓋」を使うこともあります。
浸ける時間は素材や液の濃度によって変わりますが、色素が抜けて淡くなるまで待ちます。液が濁ってきたら交換のタイミングです。
この工程で花材の水分が脱水され、元の色味が抑えられてから、次の着色・保存のステップに移ります。
ステップ3:着色・保存液浸透
脱色後、着色液または保存液へ移します。好みの色を作る場合は、グリセリン+水などをベースに染料を少しずつ加えて色を調整することもあります。
花材を着色液に浸ける際には、ムラが出ないようにゆっくり動かしたり、ピンセットで調整したりするとよいです。時間をかけて色がしっかり染み込むようにします。
着色が完了したら、花材を液から取り出し、表面の余分な液を優しく落としておきます。
ステップ4:乾燥
着色後は、花材を乾燥させます。風通しの良い日陰で自然乾燥させるのが基本です。複数の花を同時に処理する場合は、花同士が重ならないよう配置します。
急いで乾かそうとドライヤーを使う方法もありますが、熱風が強すぎると花びらが割れたり色むらを生じるので、温度と風量に注意が必要です。
この乾燥がしっかりできているかどうかで、完成後の強度や見栄えが大きく変わります。
実例:バラ vs あじさいでの違いとコツ
- バラ
バラは花びらが厚く、形を保ちやすいため初心者にも扱いやすい素材です。ただし、花びらの重なり部分に液が入りにくいことがあるので、落し蓋を使って沈めるようにするとムラを減らせます。 - あじさい
あじさいのような小房(こぶさ)系の花材は、花弁間に空気が入りやすいため、液をゆるやかに揺らしながら浸けるとムラ軽減になります。複数回に分けて着色・保存を重ねると発色がきれいになりやすいです。
このような実例を参考に、一度試作してみることで経験が積めます。仕上がりを確認しながら次回改善点を見つけていきましょう。
まとめ
プリザーブドフラワー作りは、正しい材料と基本的な手順さえ押さえれば、初心者でも自宅で気軽に楽しめるクラフトです。
まずは最低限の道具と扱いやすい花材から始め、少しずつ経験を重ねていくのがおすすめです。材料の品質や保存環境に気をつけるだけで、仕上がりと持ちが大きく変わります。
スターターキットなども活用しつつ、「失敗しても大丈夫」という気持ちで取り組めば、作る楽しさも広がるはずです。あなたもぜひ、世界に一つだけのプリザーブド作品を楽しんでみてください。